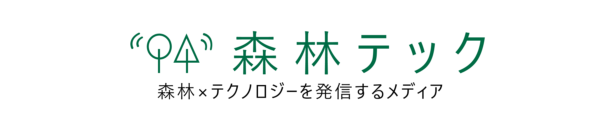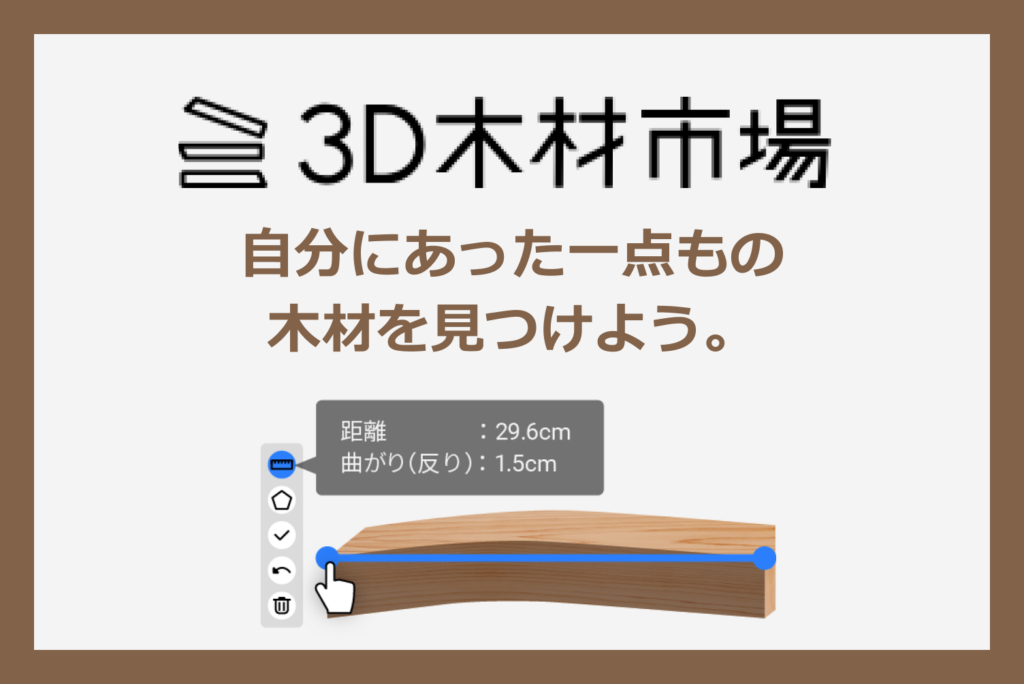近年、林業は機械化が進み、生産性の向上に貢献しています。
以前は伐採搬出に関する林業機械がメインでしたが、とくに最近は下刈りを行える造林機械の開発が進んでいて、「造林機械にはどんなものがあるんだろう」「最近の下刈りのトレンドは何?」などと考える方もいるでしょう。
そこで本記事では、2024年現在の下刈りのトレンドや下刈り機械について紹介します。
下刈り機械の動向を知るための参考にしてください。
目次
下刈りは苗木の育成に欠かせない作業
下刈りは、植栽後の苗木を育成するためには欠かせない作業です。
なぜなら、下刈りには苗木の成長を邪魔する下草を抑える目的があるからです。
下刈りについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
下刈りの概要や方法、危険なポイントなどを解説しています。
最近の下刈りのトレンド
最近の下刈りのトレンドは「隔年刈りでの省力化」と「下刈り機械の開発・活用」です。
ここでは、それぞれについて紹介していきます。
隔年刈りでの省力化
隔年刈りとは、1年おきに下刈りすることを指します。
従来よりも下刈りの作業回数が減るため、大幅な省力化が見込めます。
ただし、実際に隔年刈りで作業するには、「下刈りを省く年の苗木」が下草に埋もれていないことが条件です。
そのためには、下草があまり育たない場所や、大苗(大きい苗木)を使用することなどが求められます。
林野庁によると、コスト削減を実現した結果が報告されていて、費用の内訳は以下の表の通りです。
下刈りを省略できる効果は大きく、大苗の使用や植栽本数の削減を組み合わせて最終的なコストが抑えられたようです。
今後の作業モデルとしての普及が期待されます。
下刈り機械の開発・活用
昨今は、林業の人手不足解消と下刈り作業の効率化を目的として、下刈り機械の開発が進んでいます。
下刈り機械とは、主に下刈りが行える林業機械のことを指します。
人力の刈払い機による作業よりも、安全で効率の良い作業が可能です。
乗用式やラジコン式で下刈り作業する機械や、車両系建設機械にアタッチメントとして付けて作業するものなど、機種のバリエーションも豊富にあります。
今後は、作業システムの検討も進み、ますます普及してくることでしょう。
下刈り機械の紹介4選
下刈り機械には、主に以下の4つの作業機械があります。
- リモコン式下刈り機械
- 乗用式下刈り機械
- アタッチメントを装着した車両系建設機械
- 刈払い機
これまでは刈払い機による下刈り作業が一般的でしたが、現在では下刈りに様々な機械が用いられています。
ここでは、下刈り機械について紹介していきます。
1.ラジコン式下刈り機械
筑波重工株式会社の「ハイドロマチック・モア」
出典:林野庁「下刈り作業省力化の手引き」
下刈り用のアタッチメントが付いた下刈り機械を、ラジコンで操作するのが「ラジコン式下刈り機械」です。
遠隔操作によって下刈り機械を動かせるため、作業者の安全が確保されやすい特徴があります。
例えば、傾斜のきつい林地での作業中に造林機械が転倒してしまっても、作業者は機械とは離れたところにいるため無傷でいられます。
蜂による刺傷も心配ありません。
代表的な機械には、筑波重工株式会社「ハイドロマチック・モア」などがあります。
地拵えの除根作業にも対応できる機械もあるため、地拵えから下刈りまで幅広い造林作業が可能です。
2.乗用式下刈り機械

下刈りが可能な林業機械に作業者が乗り込んで操縦するのが、「乗用式下刈り機械」です。
下刈り機械に乗って作業することで、刈り場を目視しやすいメリットがあります。
そのため、山の微妙な起伏を読み取ったり、伐根などの障害物を避けやすかったりします。
ただし、造林機械が転倒したときの危険性は高いデメリットがあります。
刈り場を目視しやすいメリットを生かして、慎重な運転が求められるでしょう。
ラジコン式下刈り機械と同様に地拵えも可能なタイプもあるため、複数の用途に使える林業機械です。
代表的な機械には、株式会社筑水キャニコム「山もっとモット」などがあります。
3.アタッチメントを装着した車両系建設機械

車両系建設機械へのアタッチメントを変えることで、下刈りや地拵えが可能になります。
車両系建設機械のアタッチメントを変えるタイプの下刈り機械には、以下のメリットがあります。
- 空調の効いた空間で作業できる
- 蜂による被害の心配が少ない
- 一貫作業システム採用時には機械の回送を省ける
アタッチメントの種類によっては、枝条や伐根をつかめるタイプも存在します。
そのため、林地内の片付け作業が伴う一貫作業システムとの相性が良い下刈り機械です。
一貫作業システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
機械の本体はバックホーなどの車両系建設機械をベースにできるため、伐採搬出や造林作業にも使えます。
4.刈払い機

現在も多くの下刈り現場で用いられているのが刈払い機です。
肩掛け式や背負い式、一本棒式など多様なタイプの刈払い機があります。
昔は鎌での作業が一般的でしたが、刈払い機が普及したことで1日に刈れる量が飛躍的に向上しました。
しかし、熱中症や蜂刺されといったデメリットも存在します。
それでも、人力の刈払い機による作業が必要な現場はまだまだ多く、下刈り機械に全てを任せられない現状があります。
まとめ
効率よく造林作業ができるかどうかは、再造林を進めるためにも重要な課題です。
下刈り作業の省力化がトレンドの現在、下刈り機械の活用も外せない要素の1つになっています。
下刈り機械には多様な種類がありそれぞれ特徴は異なるため、地域の地形や取り入れる作業システムなどを考えた上で適切な機械を選ぶ必要があります。
今後は、各現場で下刈り機械と刈払い機を上手に組み合わせた作業システムが広がっていくことでしょう。
この記事が下刈り機械を知るための参考となれば幸いです。
参考資料
林野庁.下刈り作業省力化の手引きhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/houkokusho/attach/pdf/syokusai-17.pdf(2024年5月15日取得)