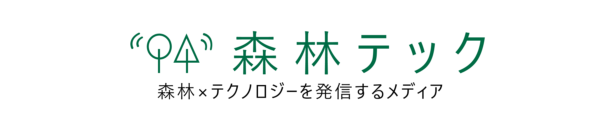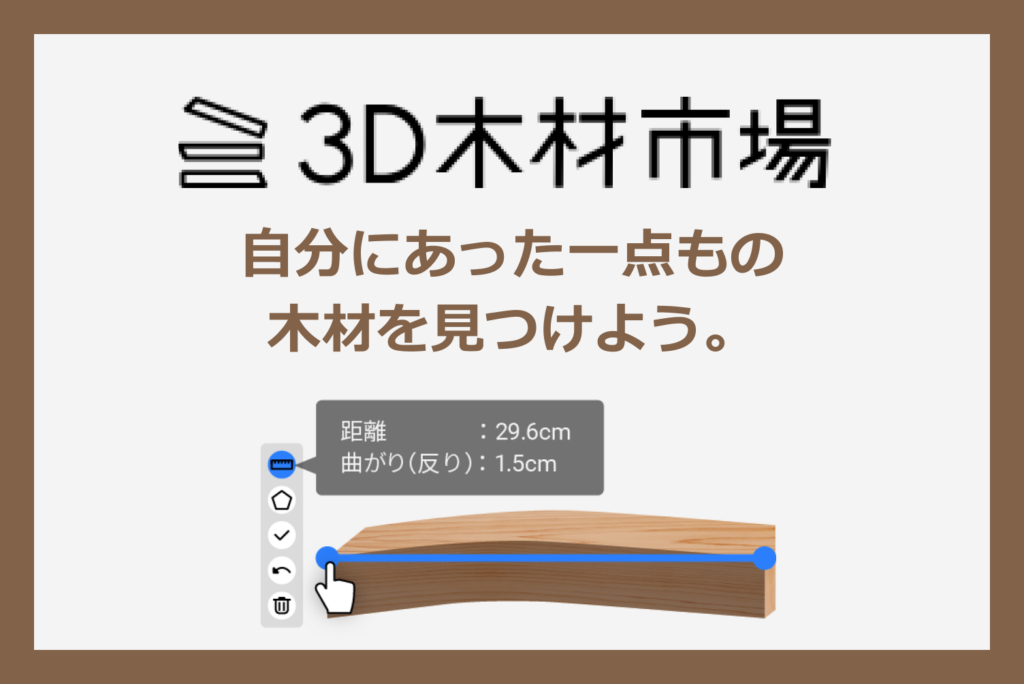林業において、植栽後に行う欠かせない作業が「下刈り」です。
下刈り作業の厳しさは、林業従事者であれば誰しも経験したことがあるでしょう。
しかし、実際に作業をしたことがない人からすると、「どんな作業をするんだろう」「何を目的に下刈りってするの?」「作業のコツがあれば知りたいな」などと思われるかもしれません。
そこで本記事では、下刈り作業の概要や方法、コツなどを紹介します。
使う道具や注意すべきポイントも解説するので、下刈り作業を知るための参考にしてください。
目次
林業における下刈りとは?
下刈りは、目的とする樹種の成長を阻害する下草を刈り払う作業です。
基本的には植栽から7年程度行われます。
作業する季節は6〜8月頃で、林業の中でも一番といってもいいほど体力的にきつい作業です。
植栽後に下刈り作業を行わずにいると、下草が大きく成長してしまい苗木が下草に隠れてしまいます。
その結果、育てるべきスギやヒノキの苗木に日の光が当たらず、健全に育ちません。
下草を刈ることで風通しもよくなるため、苗木の健全な育成には下刈りは欠かせない作業です。
下刈りの必要性は研究でも明らかになっています。
鹿児島大学の研究によると、下刈り回数が減少するにつれて、直径・樹高ともに小さくなり、植栽木の生存率の低下や曲がり発生が多くなる傾向が明らかになっています。
下刈りの方法
下刈りは育てたい樹種の周りをどのようにして刈るかによって、以下に示す表のように分かれます。
| 下刈りの名称 | 刈り方の特徴 |
| 全刈り(ぜんがり) | 植栽したエリアの全域を刈る |
| 筋刈り(すじがり) | 植栽した列に沿って列状に刈る |
| 坪刈り(つぼがり) | 植栽木の周囲だけを刈る |
下刈りといえば、一般的には全刈りを指します。
全刈りを行うことで植栽木への風当たりが心配されるときは、筋刈りを行う場合があります。
残した草木が風よけの役目を果たすからです。
坪刈りは作業にかかるコストを抑えられるため、費用をかけられないときなどに採用されます。
下刈りで使う主な道具
下刈りで使う主な道具は、刈払い機と鎌(カマ)・鉈(ナタ)です。
ここではそれぞれの特徴を解説していきます。
刈払い機

刈払い機はエンジンを搭載した棒状の機器の先端に、回転する刃物がついた機械のことです。
刈払い機には装着方法や形状の違いによって以下の種類があります。
- 肩掛け式
- 背負い式
- 一本棒式
いずれのタイプも人間が持って操作するものであるため、狭いところでも自由自在に動かすことが可能です。
植栽木を避けて雑草を刈る必要のある下刈りにおいては、刈払い機はなくてはならないアイテムの1つです。
作業時には高速で刃が回転することで雑草を刈り払うため、危険を伴う作業でもあります。
また、植栽木に刃先が触れると簡単に切れてしまうため、作業の際には細心の注意が必要です。
鎌・鉈(カマ・ナタ)

刈払い機が普及するまでは鎌による下刈りが行われていました。
現在は刈払い機による作業が一般的ですが、より丁寧な作業を求められる場合には鎌で作業することもあります。
鎌で坪刈りを行い、草の残った部分を刈払い機で全刈りするといった、作業を組み合わせた方法が取られることもあります。
鎌で刈り取りとれないような、少し堅めの木やつるを切るときに使うのが鉈(ナタ)です。
鎌を用いる作業のときには、鉈とうまく使い分けた作業が行われます。
下刈り作業のコツ
下刈り作業のコツは水平方向に刈ることです。
水平方向ということは、斜面に対して真っすぐ横方向に刈ることを指します。
下刈りの作業をする際は、水平方向に刈ることで以下のメリットが得られます。
- 上下に動くことが少なくなり歩く負担が減る
- 植栽木の場所が予測しやすい
水平方向に歩くことを意識すると横方向への動きが増え、斜面を登る回数が減ります。
その結果、作業効率の上昇や疲労の蓄積による事故防止の効果が期待できます。
また、植栽木は基本的に水平方向に植えられているため、水平方向に刈ることで次の苗木の場所を予測することが可能です。
例えば、1本の苗木を発見できれば次の苗木は水平方向の1.5〜2m先に植えられているだろう、といった予測が立てられるでしょう。
間違って植栽木を刈ってしまうことを誤伐といいますが、誤伐を防ぐ効果も期待できます。
下刈り時の危険な3つのポイント
林業における下刈りは様々な危険が伴う作業で、安全に作業するには以下にあげる3つのポイントに注意する必要があります。
- 熱中症
- 接近・上下作業
- 蜂による被害
ここでは、それぞれについて詳しく解説していきます。
1.熱中症
下刈りは雑草の成長スピードを抑えるため、雑草が最も成長する夏の時期に行います。
そのため、熱中症には十分な対策を練る必要があります。
下刈りの現場は日陰のない場所が多く、日に照らされる時間の長い過酷な作業です。
対策としては、こまめな休憩と水分補給を基本とし、ファンによって体温を下げる空調服の装着などがあげられます。
早朝から仕事を始めることで、暑い時間帯の作業を回避することも有効な熱中症対策の1つです。
2.接近・上下作業
刈払い機は鋭い刃が高速回転している、大変危険な機械です。
そのため、近くで作業すると作業者が急に振り向いた際に刃が他の作業者に当たってしまいます。
作業者同士は最低でも5m程度は離れるように距離を保つことが重要です。
また、作業者が上下の位置で作業することも危険な行為の1つです。
作業者が上下の位置で作業を行うと、足を滑らせた場合などに他の作業者と接触してしまう可能性があります。
基本的には上下の位置にならないような位置で作業する必要があります。
3.蜂による被害

下刈りの作業時期である6〜8月頃には、蜂は巣作りなどの活動を開始しています。
下刈りの現場内に巣を作ることも珍しくないため、下刈りの最中に蜂に襲われる場面も多くあります。
蜂への対策としては、以下の装備を整えることが大切です。
- 防蜂手袋
- 空調服
- 防蜂ネット
蜂の被害を完全に防ぐのは難しいかもしれませんが、装備を整えることで蜂の被害にあう可能性を下げられます。
参考:森林総合研究所「森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために」
まとめ
下刈りは植栽直後の苗木を健全に育てるために大切な作業です。
植栽後の数年間の下刈り作業を怠ると、最終的に良質な材の収穫は期待できません。
大切な作業である下刈りですが、危険と隣り合わせの作業でもあります。
各種の安全装備品を整えたり、危険行為を避けたりすることで、下刈り作業における事故の可能性は抑えられます。
ぜひ事故のない下刈り作業を目指しましょう。
参考資料
金城智之・寺岡行雄・芦原誠一・竹内郁雄・井倉洋二.「下刈り実施パタ-ンの違いが植栽木に及ぼす影響」.九州森林研究,2011. 3,No. 64,p.56-59 https://www.agri.kagoshima-u.ac.jp/env/agri0044/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/bin110805151902009.pdf(2024年6月3日取得)
森林総合研究所.森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために.https://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/research/publication/ffpri/the_first_stage_medium_term_plan_result_collection/documents/1st-chukiseika-5.pdf(2024年5月7日取得)